查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码
壹生身份认证协议书
同意
拒绝

同意
拒绝

同意
不同意并跳过





跟着“国家队”学常见疾病诊疗活动迎来首次“跨国”合作:遵义医科大学附属医院庹必光教授、刘雪梅教授团队携手日本新潟大学高桥一也副教授,共同推出“中日携手·遵医领航——23天ESD诊疗策略实战宝典”专项活动,以基础诊疗+病例提升2大核心板块为框架,设置8大进阶模块,覆盖ESD诊疗全流程关键环节,助力系统提升诊疗能力。
内镜黏膜下剥离术(ESD)是针对无淋巴结转移的早期消化道恶性肿瘤的成熟标准治疗方式[1]。除操作难度高、并发症发生率高的十二指肠ESD,以及需与耳鼻喉科医生协作的咽腔ESD外,食管、胃、大肠部位的ESD已在日本各地多家医疗机构广泛开展。在我院,年轻医师学习ESD时,大多从胃ESD开始掌握操作技巧。每年,开展内镜工作2~5年、ESD经验为0至数十例的年轻医师会通过轮转进入我科接受培训。本文以胃癌ESD为例,介绍我科针对年轻内镜医师的培训实践内容。
我们虽未对开展ESD设置特殊条件,但认为“能顺利完成常规筛查内镜操作”是最基本的要求。稳定的内镜操作、精准的目标组织活检等ESD学习不可或缺的技能,已包含在常规筛查内镜操作中。尤其是大肠内镜插入与观察过程中至关重要的角度控制,浓缩了可应用于胃癌ESD的操作技巧,建议医师熟练掌握。因此,我们认为除ESD操作本身的指导外,还应重视提升筛查内镜操作质量的相关培训。
扎实掌握这些基础技能的年轻医师,ESD水平提升更快;反之,若忽视筛查内镜操作练习,即便积累了一定病例经验,技术水平也常难以提高。
病变范围诊断堪称ESD中最重要的工作,若此处出现失误,后续整个治疗过程都可能受影响。尤其在消化道疾病中,胃癌的范围诊断难度较高,须经过大量实践才能实现精准评估。
我们会指导医师在开展内镜检查前,首先全面掌握患者背景信息。根据幽门螺杆菌未感染胃、除菌后胃、现症感染胃等不同感染状态,诊断的关注点也需有所区别。其中,未分化型癌及除菌后胃癌的范围诊断往往难度较大,因此常常需要在术前对病变周围组织进行阴性活检(未分化癌病例必须进行)。对于这类范围诊断困难的病例,年轻医师术前开展内镜检查时,指导医师会采取一对一的方式进行现场指导。
观察过程中,放大观察虽重要,但首先应扎实掌握常规观察。通过常规观察可获取病变位置、肉眼分型、不同注气量下的病变有无变形情况等丰富信息。我们会指导医师:完成常规观察后再切换至窄带成像(NBI)观察,且镜头操作必须从病变外侧向内侧推进。尤其对于较大病变或除菌后胃癌,若从内侧向外侧诊断,易出现病变范围评估不足、判断失误的情况,需特别注意。放大观察应从低倍放大开始,操作时需谨慎,避免接触病变引发出血;随后可逐步提高放大倍数,但操作务必以“最小化、精细化”为原则,无需过度大幅度操作。诊断需依据早期胃癌放大内镜简单诊断流程(MESDA-G),系统评估黏膜结构及血管的异常情况[2]。虽诊断判断存在一定主观空间,但随着病例经验积累,诊断标准会逐渐统一,诊断准确性也会随之提升。因此,医师不仅要积累自身操作病例,还需通过接触大量病例锻炼诊断的能力,这一点至关重要。
此外,病变切除后,医师自己使用实体显微镜对切除标本进行拍摄、取材,并对比分析病理图像与内镜图像,对提升诊断能力极为有益。尽管部分医疗机构可能难以开展此项工作,但在条件允许的情况下,应积极推进。
需要注意的是,通过静态图像诊断与在实际患者检查中边拍摄边诊断,两者难度存在差异。面对实际患者时,拍摄后需立即现场完成诊断,因此要求医师具备快速诊断能力。对于经验不足的年轻医师,在共同开展ESD时,我们常由指导医师先完成标记操作,再让年轻医师进行内镜观察拍摄内镜下图像的练习。

我们会指导培训医师:在开展切除操作前,需自行制定手术方案。制定方案时需综合考虑以下因素:
重力方向
病变位置与大小
是否存在瘢痕
基于上述因素确定最优切除策略,同时,术前进行操作模拟演练也极为重要。

局部注射是ESD成功的关键,操作要点如下:
穿刺位置:瞄准能使黏膜隆起最高的部位进行穿刺。
穿刺次数:次数越少,出血风险越低。需调整针尖方向(局部注射药物会向针尖按压方向的反方向扩散),尽可能通过最少穿刺实现理想隆起效果。
胃内吸气:若胃内过度注气,会导致黏膜隆起高度降低,因此穿刺后建议在吸气的同时进行局部注射。
临床中,多数初始切开不充分的情况,问题都出在局部注射环节。通过局部注射形成易切开的黏膜隆起,快速建立黏膜瓣,是实现安全、高效ESD的关键。

局部注射后的首次黏膜切开至关重要,需在注射效果充分(黏膜隆起良好)的前提下,确保切开深度足够,以完全切断黏膜肌层。
许多培训医师初期因担心风险,难以完成充分切开。若使用Dual刀,因其刀尖长度仅2 mm,只要局部注射充分,无论是按压还是切开操作,基本较为安全。我院也常使用钩刀(Hook刀),但使用钩刀时需注意避免切开过深。
完成充分的黏膜切开后,需进一步形成黏膜瓣。在形成黏膜瓣及深入分离病变的过程中,需持续调整病变与内镜的相对位置,保持最佳操作距离。通常情况下,与病变距离越远,器械与肌层的角度越接近平行;若距离过近,器械易与肌层垂直,可能导致黏膜下层损伤,进而增加安全剥离难度。年轻医师在操作时,易因专注于动作而缩小与病变的距离,因此指导医师需及时提醒,帮助其保持合适视野。若无法维持最佳操作距离与稳定视野,需判断此时难以安全操作,及时更换操作者。

快速止血直接影响手术的安全性与效率。我院会指导医师使用Dual刀或Hook刀,在清晰观察黏膜下层的基础上进行切除操作。若发现较粗血管,应先用热活检钳等器械进行预凝固处理,再开展切除。若术中出现出血,需迅速止血;若培训医师难以独立完成止血,应及时更换操作者。若止血耗时过长,血液凝固后会影响视野清晰度;此外,若在视野不稳定的状态下继续切除,出血时的操作稳定性也会下降。因此,从预防出血与高效止血的角度出发,术中始终保持清晰视野至关重要。
关于提升ESD水平的方法,我们首先会指导培训医师,在临床现场观摩指导医师的操作。我们指导团队也会尽量将ESD操作步骤转化为可描述的要点进行讲解,但需注意:内镜操作不仅需关注屏幕画面,内镜手持操作手法、高频电刀设备的操作流程等细节,往往“百闻不如一见”,通过现场观察能学到更多实用技巧。
其次,医师需对自身操作过程全程录像,术后与指导医师共同复盘。通过讨论操作中的优点与不足,制定改进方案,以便在下次操作中优化问题环节。我科培训医师人数较多,每位医师每年分配到的操作病例约20~30例,数量有限,但坚持上述复盘方法的医师,即便在有限病例中,也能实现技术水平的稳步提升。
此外,积极参与实操培训、学术研讨会等活动也十分有效。我科已研发出非生物ESD培训模型(EndoGel),并一直将其用于年轻医师培训[3]。该模型为非生物材质,可直接使用临床常规内镜进行操作,便于开展实操练习。尤其对于首次接触ESD的年轻医师,该模型有助于熟悉ESD操作流程、练习高频电刀设备使用,建议充分利用。
同时,与本院及其他医疗机构同水平的培训医师相互交流、共同进步也大有裨益。笔者目前负责组织面向年轻内镜医师的学术研讨会,每年7月会举办ESD实操培训班。从参会情况来看,每年都有众多医师通过与同龄同行交流意见,愉快地参与培训。或许,在轻松的氛围中积累内镜操作经验,才是提升ESD水平的最大技巧。
翻译:李红平教授

当院におけるESDトレーニングの実際
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野
高橋一也
1.はじめに
早期消化管悪性腫瘍に対する内視鏡的黏膜下層剥離術(ESD:endoscopic submucosal dissection)は、リンパ節転移のない早期癌に対する確立された標準的治療である1。難易度や合併症率が高い十二指腸ESDや、耳鼻科医との協力を要する咽頭ESDを除けば、食道・胃・大腸に対するESDは日本各地の多数の施設で広く実施されている。
当院では、若手医師がESDを習得する際、まず胃ESDから手技を学び始めることが多い。例年、内視鏡を開始して2〜5年目、ESD経験が0〜数十件程度の若手医師がローテーションで当科にてトレーニングを行っている。
本稿では、胃癌ESDを例に取り、当科における若手内視鏡医のトレーニング実践について紹介する。
2.ESDをはじめる条件
ESD開始にあたり特別な条件は設けていないが、通常のスクリーニング内視鏡を滞りなく実施できることが最低限必要な条件であると考える。安定したカメラ操作や正確なターゲットバイオプシーなど、ESD習得に不可欠な技術はすでにスクリーニング内視鏡の中に含まれている。特に、大腸内視鏡の挿入・観察に欠かせないアングル操作は、胃癌ESDにおいても応用可能なテクニックが凝縮されており、習熟しておくことが望ましい。したがって、ESDそのものの手技指導に加え、スクリーニング内視鏡の質を高める指導を重視すべきであると考えている。
こうした基盤をしっかり身につけた若手医師はESDの上達も早く、逆にスクリーニングをおろそかにしている場合は、症例を重ねても伸び悩むことが少なくない。
3.診断のトレーニング
病変の範囲診断は、ESDにおいて最も重要な作業と言っても過言ではない。ここで誤りがあれば、以後の治療全体が台無しになり得る。特に消化管の中でも胃癌の範囲診断は難易度が高く、正確な評価には多くの修練を要する。
内視鏡を開始する前に、まずは患者背景の把握を徹底するように指導する。ピロリ菌未感染胃、除菌後胃、現感染胃など、感染状況により診断の着眼点は異なる。なかでも未分化型癌や除菌後胃癌では範囲診断が難しい場合が多く、事前に病変周囲からの陰性生検を行う場合も多い(未分化癌の場合は必須)。こうした範囲診断困難症例では、事前の内視鏡で若手医師が検査する際も、指導医がマンツーマンで介入している。
観察に際しては拡大観察も重要であるが、まずは通常光での観察をしっかり身につけることが重要である。病変の局在、肉眼型、送気量による変形の有無など、通常観察で得られる情報は多い。通常観察を終えた後にNBI観察へ移り、カメラ操作は必ず病変外側から内側へと進めるよう指導している。特に大病変や除菌後胃癌では、内側から外側へ診断しようとすると範囲を過小評価し、範囲を誤認する可能性があるため注意が必要である。拡大観察は弱拡大から開始し、病変に接触して出血を起こさぬよう慎重に行う。徐々に拡大率を上げるが、操作はあくまで最小限かつ精緻にすべきであり、過度にダイナミックな動きは不要である。診断はMagnifying endoscopy simple diagnostic algorithm for early gastric cancer (MESDA-G)に基づき、粘膜構造や血管の不整を系統的に評価する2。判定には主観が介在する余地があるが、症例を重ねることでキャリブレーションが進み診断精度は向上する。自らの症例に限らず、多くの症例を経験し目を鍛えることが重要である。
さらに、切除後に病変を自ら実体顕微鏡で切除標本を撮影・切り出し、病理像と内視鏡像を比較検討することは診断力向上に極めて有用である。施設によっては実施困難かもしれないが、可能であれば積極的に取り組むべきである。
静止画で診断することと、実際の患者において自ら写真を取りながら診断していくのは難易度が異なる。実際の患者の場合、写真を取ったらすぐその場で診断を行わなければならず、診断の瞬発力が必要である。慣れない初学者の先生とESDを行う際は、まずマーキングのみ指導医が行い、その後若手医師に撮影のトレーニングを行ってもらう場合も多い。
4.切除のトレーニング
a. ストラテジーの立案
切除に臨む前に、まずはトレイニー自身が戦略を立てることを指導する。
· 重力の向き
· 病変の局在、大きさ
· 瘢痕の有無
これらを考慮し、最適な切除方針を決定する。イメージトレーニングを行うことも極めて重要である。
b. 局注の工夫
局注はESD成功の鍵である。
· 穿刺位置:膨隆が最も高くなる部位を狙って穿刺する。
· 穿刺回数:少ないほど出血リスクが減る。針先の向きを調整し(局注は針先を押し付けた方向と逆に流れる)、なるべく少ない穿刺でよい膨隆ができるように工夫する。
· 胃内脱気:過送気の状態だと膨隆が低くなるため、穿刺後は脱気しながら局注するとよい。
最初の切開が不十分なケースの多くは、この局注過程に問題がある。局注で切りやすい膨隆を形成し、素早くフラップを形成することが安全で素早いESDにつながる。
c. 粘膜切開とフラップ形成
局注後の最初の粘膜切開は極めて重要である。局注が十分に入っている状況で、粘膜筋板を確実に切るように十分に深い切開を行う必要がある。
最初は怖さがあり、十分な切開をできないトレイニーも多い。Dualナイフであれば、先端が2mmであるため、押し付けても切開しても局注が十分であれば基本的には安全である。当院ではHookナイフも頻用するが、フックナイフの場合は深くなりすぎないように注意する。
十分な粘膜切開を行ったら、フラップ形成を目指す。フラップ形成時やうまく病変に潜り込んだあとも、病変とスコープの位置関係を調整し、至適距離を保つことが重要である。基本的に病変から離れるほど、デバイスは筋層に対して並行になる場合が多い。距離が近いと、デバイスが筋層に対して垂直に経ってしまい、粘膜下層も潰れてしまうため、安全な剥離が難しくなる。初学者の場合、手技に夢中になると病変とスコープの距離が近くなりがちなので、指導医はトレイニーが適切な視野を保てるように指導を行っている。こういった至適距離、安定した視野が保てない場合は、安全な操作困難と判断し、手変わりするようにしている。
d. 血管の処理と止血
素早い止血は処置の安全性・スピードを左右する。当院ではDualナイフやHookナイフを使用し、粘膜下層をしっかりと視認しながら切除するように指導している。その際、太い血管があった場合は事前にコアグラスパーなどでプレコアグレーションを行ってから切除する。出血した場合は速やかな止血が求められるが、トレイニーが止血困難な場合は早めに手変わりする。止血に時間がかかると、血液が凝固してしまい、視野確保が難しくなる。
また、不安定な視野のまま切除を進めると、出血時の操作も不安定になってしまう。そのため、安定した視野を常に確保することが、出血予防および止血の観点からも重要である。
5.ESD上達のためのtips
ESD上達のコツとして、指導医の手技を現場で見学するように指導している。我々指導医はESDの手技をなるべく言語化して指導するように心がけている。しかしながら内視鏡の画面だけではなく、内視鏡の手元の操作や、高周波装置のステップワークなど、百聞は一見にしかずで、見て学び取ることは多い。
また、自分の手技は必ず録画し、後で指導医と振り返るべきである。良かった点、悪かった点をディスカッションし、次の手技では悪かった点を克服できるよう、工夫が必要である。当科はトレイニーの数が多く、1人あたりが1年間に割り当てられる症例は20−30例程度と限られる。しかしながら、上記を実践しているトレイニーは限られた症例数のなかでも、着実にレベルアップしている。
また、ハンズオンやトレーニングセミナーなどを利用することも有効である。当科では、非生体トレーニングキットであるEndoGelを開発し、これまで若手のトレーニングに使用してきた3。本モデルは非生体モデルであり、患者に用いる内視鏡をそのまま使用することができ、手軽にハンズオンが実施可能である。特にESDを初めて行う初学者の先生にはESDの雰囲気や、高周波装置のステップワークの練習になると思うので、ぜひ活用していただきたい。
また、自施設や他施設の同じくらいのレベルのトレイニーと切磋琢磨することも有益であろう。筆者は若手内視鏡医を対象とした研究会の世話人を努めており、毎年7月にESDのハンズオンを開催している。参加者の様子をみると、毎年多くの先生方が同世代の仲間と意見を交換しながら楽しそうに参加している。楽しみながら内視鏡修練を積むことこそ、最大のコツかもしれない。
ESD适应证及基本操作技巧 | 中日携手・遵医领航②
作者:遵义医科大学附属第一医院 石国庆
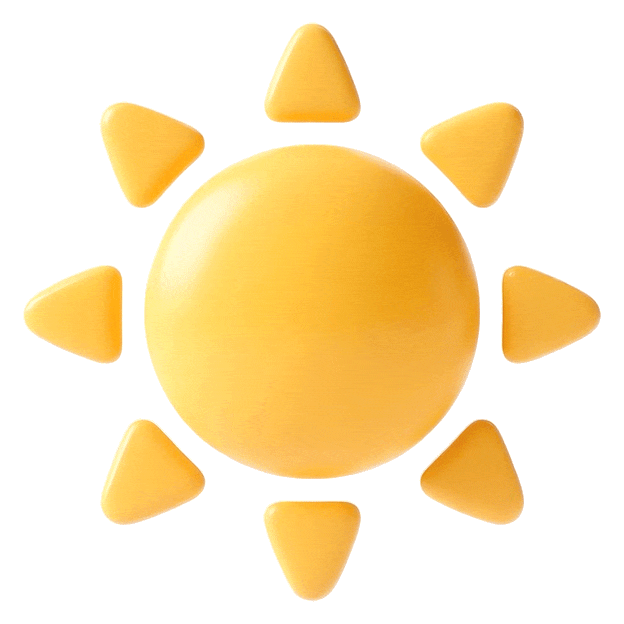
查看更多